

クレラー・ミュラー美術館 ゴッホの「郵便配達夫」
☆☆☆


クローラ・ミューラー国立美術館
今回の旅でも幾つもの画を眼にしてきた。ベルギーではアントワープでルーベンス、
ゲントのファン・エイク兄弟、ヨース・ヴァン・ワッセンボフなどを見た。
ヨーロッパは何処へ行っても優れた芸術家の作品に事欠かないが、何と言ってもオ
ランダでは絵画の国と言っていいほど。あまりに有名なゴッホをはじめとし、レンブ
ラント、フェルメールなどお馴染みの大家がこの国から出ている。
ハーグでは、私たちのホテルの隣にはオランダ近代画家の代表ピート・モンドリア
ンの収集をほこる市立美術館があったし、市内にはフェルメールの最も人気作品であ
る「青いターバンの少女」があるマウイリッツハイス美術館もあった。明日移動する
アムステルダムには国立ミュージアムと並んでゴッホ美術館など絵画芸術を巡る観光
客を飽かす事はなさそうだ。
フェルメールで有名なマウイリッツハイス展が夏に東京で開催されるので、ここで
はそれを割愛するのは致し方ないとしても、この旅のメニューに、アムステルダムの
ゴッホ美術館が含まれていなかったのが残念だった。しかし、その代わりというか敢
えて東部に足を伸ばし、クローラ・ミューラ国立美術館を観ることが出来たのは幸い
した。
ハーグからユトレヒトを経由して大戦終盤の悲劇映画「遠すぎた橋」の舞台アーネ
ムに近いオッテルローまで約110kmを走る。静かな田園風景と織り成して現れる
街では窓に眼を凝らしてオランダらしい風景を探す。
オランダの建物は窓が白い縁取りで明るい、これが北欧へ行くと「黒い」とのこと
であるが、天候が変わりやすく曇りがちな風景に明るさを添える希望を適える窓への
憧れであろうか。白い自転車も幾つも走っていた。沿道の林には松の木も多い、他は
白樺、椚か?そう見ると日本にも共通する。
オッテルローの広大なホーヘ・フェルウェ国立公園は、5500ヘクタールもの敷
地からなるオランダ最大の国立公園である。広大な公園内には12の散策コースや無
料貸出自転車があるという。公園に入れば美術館も含めて自由に過せる。
その真ん中にあるクレラー・ミュラー美術館は、クレラー・ミュラー夫妻がコレク
ションをオッテルローの森と共にオランダ政府に寄贈して誕生したものである。建物
はアール・ヌーボー建築の旗手アンリ・ファン・デ・フェルデが設計した平屋建て建
築、入り口の芝生にはクレラー夫妻の頭文字を使ったオブジェが飾られていた。
多くのゴッホ・コレクションで世界的に有名になり、アムステルダムのゴッホ美術
館とともに、オランダ2大ゴッホ美術館と言われている。
2時間の自由鑑賞が許されたので終始、ゴッホの作品に近づいていった。
自然光が室内に及ぶ感覚の明るい展示室で、しかも自由に撮影が許され、たっぷり
充実した鑑賞の時を持つことができた。
「ゴッホの波乱に富んだしかも短い人生に於ける画家としての本領が発揮されたの
は、彼が画家として絵筆を持った27歳から37歳までの10年のうちアルル、サン
・レミ、オーヴェールでのたった3年間にしかすぎない。」と、評する人(中山公男
=集英社世界美術全集)もいるくらいだ。人生の波乱だけではない、生前は大した評
価もされず、病は不幸な死さえも招いた。しかし、不吉な予感のテーマと言われる作
品こそ希少にあるとは言うものの、印象派の盛り上がった時期に相応しいと言うべき
か、画から流れれ出る旋律は、静かで明るいイメージが多いと私は思う。「アルルの
跳ね橋」や「星空のカフェテラス」、花を背景に散りばめた「郵便配達夫」など好き
な絵が居並ぶ数々の作品に混じってゆっくりと眺められる至福の時であった。
そればかりか、彼のパリへ出る前の遍歴時代の展示品を沢山見ることが出来た。こ
とに数多くのデッサン画はここに来ずしては近寄れないものかと思った。
ゴッホの画に対する導入は、エッテンの実家周辺で田園風景や近くの農夫たちを素
材に素描や水彩画に親しんだことに始まったのである。そしてハーグでモーヴから油
彩画、水彩画の指導を受け、2人の関係が悪化した後には、父親が移り住んでいたオ
ランダ北ブラバント州ニュネンに移るが、アイントホーフェンの東郊の農村に帰省し
(1883年末−1885年)数年間にわたって描き続けた農夫の人物画の集大成と
して、彼の最初の本格的作品と言われる「ジャガイモを食べる人々」を完成させたの
であった。
その画はゴッホ美術館にありここでは観ることが出来なかったが、エッギングで描
いた「草を刈る農夫」、働く農夫、休息する農夫などを私はあらためてしみじみと観
て来た。
ゴッホの他にもヤン・ステーン、スーラ、ブラック、ピカソ、モンドリアンなどオ
ランダの黄金時代といわれる時代の作品、さらにミレー、セザンヌなど印象派の有名
な作品があって名残惜しかった。
鑑賞に疲れて美術館周りの庭園ロダン、ブーデル、マリーニ、ムーアなど多くの彫
刻が時を癒してくれた。思いがけず、散策中に会社勤務をしていた頃の同僚H氏に出
会った。夫妻で来ているとのことで懐かしい思い出話をしたりもした。
アムステルダム国立博物館
翌日の午後、アムステルダム国立博物館に入った。オランダの歩みを物語るとの触
れ込みでコレクションの数々は、1100年から現在まで世界史の流れに沿ってオラ
ンダ史を見ることができるとのことであった。今、改修中で、作品は一部分散して展
示されていた。
私は絵画として歴史的、あるいは文化的に大きな価値を持ち、アムステルダム国立
博物館最大の見どころと言われる作品を観ようと心がけ、「肖像画」のフランス・ハ
ルス、17世紀バロック期の「農民」を描いたヤン・ステーン、日本へもやってくる
と言うフェルメールの「牛乳を注ぐ女」など、17世紀の巨匠たちの代表作を観た。
しかし、会場に迫る大作、レンブラントによる「夜警」がその場の人気もあって何よ
りもこの会場の印象を高めていた。
「夜警」は1640年の末に火縄銃手組合が発注した集団肖像画として描かれたも
のであるが、レンブラントは独自の主題性と動きのある構図を用いて、2年もかけて
完成させたと伝えられる力作である。
彼は大画面と、明暗を画面上に強く押し出した光と影を創り出す技法、ルミニズム
の技法を得意とし、「光の画家」「光の魔術師」(または「光と影の画家」「光と影
の魔術師」)の異名で称えられたが、この画で頂点を極めたかのように、その後のレ
ンブラントは沈んでいく。
芸術家の生涯は往々にして順調な例が少ないようではある。
すぐ近くの場所にはファン・ゴッホ美術館もあって、持ち時間の少ないツアーに残
念至極であったがそれも当方の事情、すべて叶えられることは贅沢と言うものかと未
練のうちに博物館を出た。
館の修理はまだあと1年は要すると言う。出来ることならいつの日か、もう一度ゆ
っくり訪ねてみたいものだと思う。
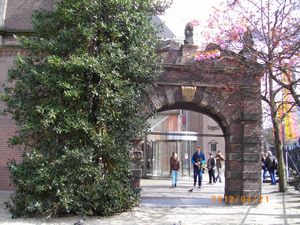

アムステルダム国立博物館 フェルメールの「牛乳を注ぐ女」
* 西欧の春の旅(13)
* 風次郎の「東京ジョイライフ」ホームページのトップへ
* 『風次郎の世界旅』 トップページへ戻る
* 風次郎の『八ヶ岳山麓通信』へ
* 風次郎の『善言愛語』へ