☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
風次郎のColumn『東京楽歩』 (No649T−161)
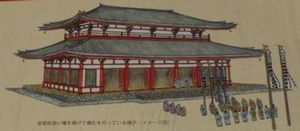
武蔵国分寺金堂復元図
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
風次郎のColumn『東京楽歩』 (No649T−161)
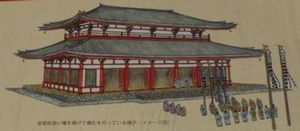
武蔵国分寺金堂復元図
――国分寺史跡へ向かう最寄りの駅は勿論JR国分寺と言うことになろうが、西国分寺
の駅からでもそう変わりはない。国分寺駅からは約15分。南口からやや右手の交番の
先都道145号立川国分寺線(多喜窪通)を国立方面に向かう。いったん野川の源流まで
下り坂になるが、再び坂道を登りきったところにある小林理学研究所を過ぎたとこで左折
すると、都立武蔵国分寺公園に入る。森を抜けると国分寺の境内である。
西国分寺駅からとすると、やはり南口を出て、ロータリーをやり過ごし史跡通りと称する
団地内の並木通りを進むと、多喜窪通りと府中街道に掛かる陸橋にぶつかる。陸橋を渡
って50m先を右折すれば、そこには旧東山道の(復元)史跡があるのでこれを見逃さない
ようにして先へ進めば、立川崖線の坂を下って史跡に着く。坂道の左側消防署の裏側が、
武蔵国分寺の薬師堂である。――
☆
東京楽歩(No161)国分寺史跡樂歩(5)
(概要 大半の資料は現地展示、資料館より収集させていただきました)
府中方面から参道をたどり、南門から七重の塔へ廻って中門跡で再び史跡の中央部に
立った。
中門と金堂の間には伽藍中軸線上に東西に並ぶ2列の大きな穴が幾つも検出され、これ
は幢竿(どうかん)の痕跡と推定されている。幢竿とは宗教儀礼の際に装飾として用いる幡
(はん)を吊り下げる柱のことである。
金堂から南側20mと35mの位置にそれぞれ4本一組、2本一組、30cmの太さと推定さ
れる柱跡であったという。当時、金堂の正面を儀礼空間として旗竿のように竿に幟(のぼり)
を掲げて祀った場所のようである。
正面の金堂跡は昭和の発掘の時に大きく整備され、参道から一段高い地盤が石垣を積
み上げて整備されている。
訪れる参観者の利便と史跡の実感を導くためにレンガが敷かれているが、その先の講
堂に至る通路と講堂跡までを見渡すとその規模の大きさを感じ取ることができる。
基壇に上がって右に回り、まずは鐘楼の跡を眺めたあと、あらためて金堂跡を眺めた。
金堂
金堂は本尊仏を安置する仏殿で、塔とともに寺院を構成する重要な建物である。
ここには本尊である釈迦如来像と脇侍菩薩像(文殊菩薩・普賢菩薩)四天王像(持国天・
増長天・広目天・多聞天)が安置されていたという。
武蔵国分寺の金堂は四周に廂(ひさし)を伴う礎石建ての建物で、桁行(けたゆき)7間、
梁行(はりゆき)4間の規模を有し、基壇上に本来36個据えられていた礎石は、現在19
個が残っている。(後世に持ち去られて無くなった場所には同じ円形の礎石が補充されてい
る)
建物を乗せる基壇の外装は乱石積を施し、外周に幅約1mの雨落石敷が巡り、南面と北
面中央には石積みの階段を伴う。礎石と雨落石敷の高さの差から、基壇の高さは約70〜
90cmあったものと想定されている。また、北階段は建物中央の柱間1間分の幅であるの
に対して、南面の階段はその約3倍の規模があったことから、建物は南側を正面としていた
ことが判るとのことである。
基壇を造成するにあたっては、建物より一回り広い範囲に対して、地面を約1.3m掘り
下げ、その中はローム土・暗茶褐色土・黒色土を交互に版築する掘り込み地業を施した後、
基壇も同様に版築で積み上げている。さらに、個々の礎石の下部には役2m四方、深さ1m
程の堀込みを伴い、石と土の互層による版築で突き固めた坪掘り地業を行っていた様子が
発掘調査で明らかになった。
また、建物の屋根は入母屋造りもしくは寄棟造りで、廂を支える礎石と雨落石敷までの距
離から、軒先の出は16〜17尺程度(約4.8〜5.1m)と想定され、国分寺の金堂と
しては全国でも最大級の規模と荘厳さを誇っていたことが想定されるという。
金堂の西側(正面から左手)には経蔵があったとされ、また東の鐘楼跡の外側と西の経蔵
の外側にはそれぞれ東僧房、西僧房が置かれていたという。現在これらのうち鐘楼以外の
発掘は定かでない。
風次郎


中門跡から金堂基壇を見る 基壇と柱跡
メルマガ・風次郎の「東京ジョイライフ」「東京楽歩」No162へ
メルマガ・風次郎の「東京ジョイライフ」トップへ
風次郎の「東京ジョイライフ」ホームページのトップへ
風次郎の「八ヶ岳山麓通信」のトップへ
風次郎の「世界旅」へ