☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
風次郎のColumn『東京楽歩』 (No645T−159)

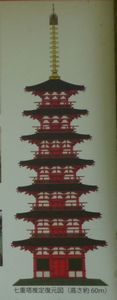
参道復元道路 七重の塔復元図
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
風次郎のColumn『東京楽歩』 (No645T−159)

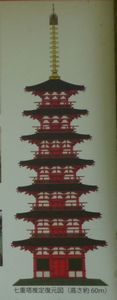
参道復元道路 七重の塔復元図
東京楽歩(No159)国分寺史跡樂歩(3)
(概要 大半の資料は現地展示、資料館より収集させていただきました)
参道口から僧寺へ
武蔵国分寺は、都と国府を結ぶ駅路(東山道武蔵路)の、その東側に僧寺、西側に尼寺と
配された。いまの両史跡は、丁度府中街道とJR武蔵野線を挟んだ格好の配置となっている。
南門から府中寄り約400mのところに参道口がある。
府中市の万作の木公園となっている場所である。そこには参道口門柱状遺構と道路跡があ
り、二方向に分岐している処が復旧されている。2.2〜3m幅の道路であるが先の参道は
6mまで広がっているようだ。北側へまっすぐ行くと僧寺、もう一方北西へ向かう道路は東
山道武蔵路と武蔵国分尼寺へ向かっている。
ここは当時武蔵の国の国府(現在の大國魂神社地点)から北に約2kmの地点である。
発掘では道路跡両側にまたがった柱列跡が3基見つかっており、それぞれは別々の時期に
建て替えられた直径34〜45cmの柱痕跡であった。上部がどのようになっていたかは明
らかではないが、2本の柱の存在は、参道口を指し示す標識としての柱か、冠木門のような
横木を一本渡した門であったと推定されている。
現在参道は住宅地とその先にできた東八道路のなかに隠れてしまっているが、ほぼ僧寺へ
の参道に沿ったまっすぐな住宅地の中の道を北に辿ると、僧寺の南門跡があり、そこが金堂
や講堂を囲んだ溝の存在した域であるとの標識がたっている。
当時、武蔵の国は多摩郡をはじめとする21郡からなり、国分寺の造営にあたっては武蔵
国内の人々の力が総結集されたのであったが、出土された土器や瓦、漆紙文書などから完成
された年代は天平宝字年間(757〜765)頃と考えられている。
僧寺は中枢部、伽藍地、寺院地の三重に区分される構造であり、中枢部には北から順に、
経典などを購読する講堂、本尊を安置していた金堂、入り口にあたる中門が主軸を揃えて一
直線に並び、その両側に梵鐘を吊った鐘楼と、経典を収蔵した経蔵、僧が起居する東僧房、
西僧坊などがあった。
これらの建物は塀と溝によって囲まれ、その規模は東西で約156m、南北で約132m
を測る。また塀の構造は、掘立柱塀から築地塀へ変わったことも明らかになっている。
中枢部の外側には、中門から南へ約60メートル離れて南門、東へ約200メートルの地
点に七重塔がそびえ、これらの堂塔は溝に寄って周囲と画されていたのである。さらに、金
堂を中心とした東西約1.5キロ、南北約1キロの範囲には竪穴住居や掘立柱建物が広がり、
寺院を支えていた集落は広域に及んでいたとされている。
僧寺の寺院地区を囲む外側と、南門跡から主要施設を囲んでの区分溝、その主要施設を囲
む溝のあたりを東に、七重の塔の遺跡に向かう。
七重の塔
聖武天皇の「国分寺建立の詔」には飢饉や疫病の流行、内政の混乱を仏教の力で治めるこ
とが謳われている。さらに国ごとに七重の塔を一基造り、金字金光明最勝王経を安置するよ
う示されており、「造塔の寺は国の華である」という記述から、七重の塔は伽藍の中でも特
に重要視されていたと言われる。
武蔵国分寺ではこれまでの調査で、2基の塔跡が発見されているが、諸国国分寺で塔が2
基発見されるのは異例である。
遺跡として発掘展示されているのは塔1である。塔2は塔1より西に約55mの場所にて
調査発掘され、塔1とほぼ同規模であったことが確認された。

メルマガ・風次郎の「東京ジョイライフ」「東京楽歩」No160へ
メルマガ・風次郎の「東京ジョイライフ」トップへ
風次郎の「東京ジョイライフ」ホームページのトップへ
風次郎の「八ヶ岳山麓通信」のトップへ
風次郎の「世界旅」へ