丂 仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛
丂丂丂丂丂丂丂
晽師榊偺俠倧倢倳倣値亀搶嫗妝曕亁丂丂
丂丂乮No374俿亅90乯
丂丂丂丂丂丂丂
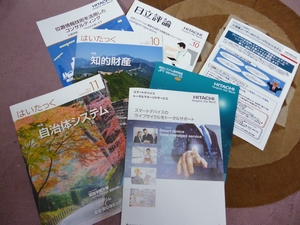
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 乽擔棫僀僲儀乕僔儑儞僼僅乕儔儉2014乿僷儞僼丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂
丂丂 仚仚仚仚仚仚仚仚仚仚仚仚仚仚仚仚仚仚仚仚仚仚仚仚仚仚仚仚仚仚
丂 仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛仛
丂丂丂丂丂丂丂
晽師榊偺俠倧倢倳倣値亀搶嫗妝曕亁丂丂
丂丂乮No374俿亅90乯
丂丂丂丂丂丂丂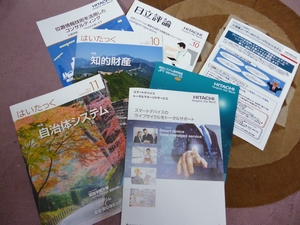
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 乽擔棫僀僲儀乕僔儑儞僼僅乕儔儉2014乿僷儞僼丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂俀侽侾係擭侾侾寧
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂搶嫗妝曕乮俶倧90乯
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 擔棫僀僲儀乕僔儑儞僼僅乕儔儉2014
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂Hitachi Innovation Foyum2014偑侾侽丒俁侽乣俁侾丄崱廡桳妝挰偺搶嫗僼僅乕儔儉偱
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂奐偐傟偰偄偨丅埲慜偐傜埬撪傪懻偄偰偄偨偺偱嶲壛偟偰棃偨丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂擔棫僌儖乕僾偑憤椡傪嫇偘偰峴偭偨僀儀儞僩偱丄宖偘傜傟偨僥乕儅偼丄亀恖乆偺枹棃
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂傪戱偔僀僲儀乕僔儑儞乣忣曬妶梡偑妚怴偡傞價僕僱僗偲幮夛乣亁丄儌僲嶌傝偐傜憤崌摑
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂崌嶻嬈傊丄偝傜偵僌儘乕僶儖壔偵岦偗偰擛幚側庢傝慻傒傪悑偘偰偄傞傗偵尒偊傞擔杮偺
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂戙昞揑婇嬈孮傜偟偔丄壺乆偟偔傕桳堄媊側僼僅乕儔儉偩偭偨偲巚偆丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂梫偼俬俿傪嬱巊偟偰忣曬傪擛壗偵妶梡偡傞偐丄幮夛栤戣偐傜屌桳偺儅乕働僥傿儞僌傑
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂偱偦偺巺岥傪扵傝丄埥偄偼儊僨傿傾偲嫟偵採嫙偟偰偄偔巔惃傪戝偄偵傾僺乕儖偟偰偄偨丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂巹偼丄偄偔偮偐偺僽乕僗偱嬶懱揑側僥乕儅偵婎偯偄偰揥帵偝傟偨僴乕僪傗帒椏僷僱儖
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂傪挱傔側偑傜丄乽偙偺崁偱擔棫偑撈摿偵僾儗僛儞偱偒傞傕偺偼壗偐乿側偳偲丄惗堄婥偵
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂幙栤偟偰傒偨偑丄庒偄扴摉幰偨偪偼墳梡栤戣偵偼擬偺偁傞僐儊儞僩傪尰傢偝側偐偭偨傛
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂偆偵巚偆丅傕偟偐偟偨傜摉曽偲偺傗傝庢傝偑丄愭曽偵帒偡傞偵媦偽側偐偭偨偺偐丄偄傗
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂偦偆偱偁傠偆丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂椺偊偽丄價僢僌僨乕僞偼偦偺庢埖偄偵僨儕働乕僩惈傪敽偭偰偄傞偑丄帶崱昁慠揑偵廳
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂梫帇偝傟傞偲巚偆丅偦偺拞偱慖嫇偺弌岥挷嵏偲偄偆僾儔僀儀乕僩忣曬偼嬌傔偰摉棊梊憐
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂偵懳偟偰崅偄妋搙偱偁傞偲巚偆丅偟偐傜偽丄偦傟傪墳梡偟偨價僕僱僗偼偳偺傛偆偵揥奐
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂偝傟傛偆偐偲偺幙栤偵擬慄傪姶偠偝偣傞扴摉幰偼偄側偐偭偨丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂巹尒偱偼偁傞偑丄偙傟偐傜偺僌儘乕僶儖忣曬壔幮夛偵墬偄偰偼丄幮夛偲偺僶儔儞僗偺
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂椙偄僐儈僯働乕僔儑儞偼擛壗側傞暘栰偵偁偭偰傕儀乕僗偵側傞丅側傟偽偙偦丄俬俿偺恑
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂壔傪椊夗偡傋偔丄婇嬈偵偁偭偰偼丄嵞傃屄乆偵偍偄偰幮堳嫵堢搳帒偵廳偒傪抲偔帪戙偲
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂側傞傛偆側婥偑偡傞丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂傕偪傠傫偙偺僀儀儞僩偺傛偆偵丄幮夛偵峀偔傾僺乕儖偲懳榖傪媮傔傞婇夋偲暲傫偱偺
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂帠偱偁傠偆偑丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂亀僀僲儀乕僔儑儞亁偑僥乕儅偱偁傞偵憡墳偟偔僲乕儀儖宱嵪妛徿偑尐偵晅偄偨榖戣偺
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂恖丄僾儕儞僗僩儞戝妛偺億乕儖丒僋儖乕僌儅儞巵偺島墘偑偁偭偨丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂摨帪捠栿傕揙掙偟偰偄偨偑丄偝偡偑偵慡悽奅懡曽柺偱応悢偺巘丄柧夣側榑巪偲巹偵傕
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂夝傞塸岅偱桳擄偐偭偨丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂偛嶲峫傑偱偵巹偺暦偒庢傝儊儌傪晅婰偟偰偍偒傑偡丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乗乗乗俀侽侾係丏侾侽丏俁侾億乕儖丒僋儖乕僌儅儞島墘乗乗乗
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂傾儀僲儈僋僗偺昡壙偲栤戣
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂僌儘乕僶儖宱嵪偵懳偡傞埵抲偯偗偲偟偰丄innovation偺廳梫惈偼崅偄丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂擔杮偼侾侽俉侽擭戙搚抧奐敪偱宱嵪傪墴偟忋偘丄偼偠偗偰丄埲屻挿婜掆懾忬懺偵娮偭偨丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂巵偼俀侽侽侽擭偵僾儕儞僗僩儞偵惾傪抲偄偨偑丄Japanificasion(擔杮尰徾)側偳偲偄
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂偆尵梩傪巊偭偰丄帺暘傕娷傔庩偵僗僄乕僨儞偺僗儀儞僜儞側偳丄枖慜俥俼俛偵偄偨僶乕
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂僫儞僉傕擔杮傪婋湝偟偰偄偨丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂寢壥揑偵偼丄侾俋俉侽擭戙偐傜偺偙偲偼暷偲傕曄傢傜側偢丄暷傕廧戭僶僽儖偑偼偠偗丄
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂僀儞僼儗偐傜僨僼儗偵側偭偨偺偱偁傞丅扐偟丄偙傟偼杮奿揑側僨僼儗偱偼側偄丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂懕偄偰丄儐乕儘寳偑僀儞僼儗乕僔儑儞偵姫偒崬傑傟偰偄傞丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂偦偺屻丄怴嫽巗応偺戜摢偑愗曉偟偺帇揰偲側偭偨偑丄偦傟傕偦偆嫮偄傕偺偱偼側偄偲
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂夝偭偰偒偨丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂栤戣揰嘥
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乽晧嵚偑懡偡偓傞偲偄偆栤戣乿偑擔杮偵偼偁傞丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂偟偐偟丄偦偺晧嵚偵傛偭偰棙塿傪傕偨傜偝傟傞恖乆偵偲偭偰偺塭嬁偑惗偢傞偙偲偐傜丄
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂偍屳偄偵栤戣偵偟側偄偲偄偆巚憐偑惗傑傟傞偺偩丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂偦偺寢壥偑丄晧嵚偺僷乕僙儞僥乕僕偑尭彮偟側偄忬嫷傪惗傓丅偙傟偑derivalising?
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂偑惗偠偰偙側偄尰徾傪惗傓丅扐偟丄僨僼儗偺慾巭丄椺偊偽岞嫟搳帒偺弅彫側偳偼懳嶔
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂偲偟偰憡斀偡傞傕偺偱偁傞偲峫偊傞丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂栤戣揰嘦
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂儓乕儘僢僷偺娫堘偄偑偁偭偨丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂棙忋偘傪幚巤偟偨丅乗摿偵僗僄乕僨儞乗丂仺僨僼儗傪扙媝偱偒側偄丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂懳張偺尰忬
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂擔杮偼柾斖揑側懚嵼乮柾斖揑偱偁傞傋偒懚嵼丠乯偵側偭偰偒偨偲巚傢傟傞丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂惌嶔偲摨帪偵娕夁偱偒側偄secure staguflastion 亖宱嵪偑掆懾偟偨傑傑挿偄娫巭傑偭偨
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂忬懺偱偁傞丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂偙傟傊偺忢偲偆庤抜偼乽棙壓偘乿偱偁傞偑丄侽傛傝壓偘傞帠偑弌棃側偄丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂擔杮偼侾俋俋侽擭丄墷暷偼俀侽侽俉擭偐傜偺忬懺偱偁傞丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂儅僀僫僗嬥棙摍傕娷傔丄偙偺傛偆側忬嫷偼乽抁婜揑側惌嶔偺娫堘偄乿偲峫偊傞傋偒偱偼側
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂偄丅丂
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂偙傟偐傜偺帇揰
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂恖岥宍懺偺曄壔丂恖岥偼宱嵪偺婯柾偵塭嬁偡傞丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂擔杮偺応崌偼侾俋俈侽擭埲崀尭彮偟偰偄傞丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂儓乕儘僢僷偼俀侽侽俋擭偐傜偱偁傞丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂暷偼丄弌惗棪丄堏柉偱尭彮偼柍偄偑丄廇楯恖岥斾棪偼壓偑偭偰偄傞丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂宱嵪偵娭偡傞innovation乮technolozy乯丂偺僺僢僠偑曄傢偭偨丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂internet偺晛媦丄innovative technolozy乮僒僾儔僀僠僃乕儞乯側偳
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂twitter丄smart pfone丂側偳偺弌尰
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂僺乕僞乕丒僥乕儖乮pay pal憂愝幰乯摍搊応
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂媄弍揑側愻楙惈偼悽奅摨帪壔偟偰偄傞丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂惗嶻惈傗technorozy 丄嬥梈惌嶔傗捠壿惌嶔丂偺旝柇側憡堘傪帇傞
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂僄儅乕僕儞僌丒儅乕働僢僩偵栤戣
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂摿偵拞崙丂惉挿偑昻崲傪杽傔懕偗傜傟傞偐丠搳帒偑俧俢俹偺係俈乣亾
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂帺崙偩偗偑杅堈崟帤傪挋傔偙傫偱偄傞丅侾俋俉侽擭戙偺擔
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂杮偵帡偨晄摦嶻僶僽儖丂仺拝抧偱偒傞偐仺儕僗僋
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂儓乕儘僢僷偺懳張偺巇曽丂
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂暷偺愭峴偒傕晄柧偑偁傞
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂偙傟偐傜偺懳張
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂柉娫偺innovationn揥奐偵婜懸
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂擔杮偺傾儀僲儈僋僗偼丄傂偲偮偺帋傒偲偟偰丄惌嶔innovation偲偟偰惉岟偲尵偊傛偆偑丄
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂惌嶔偺response傪娫堘傢側偄傛偆偵丄
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂庩偵暷偼慡偔懠偲堘偭偨惌嶔偑昁梫乮杮棃僨僼儗傪昁梫偲偟偰偄傞乯側崙偱偁傞偟丄枖丄
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂墷暷偼捈姶偱惌嶔傪棫埬偡傞孹岦偑偁傞帠傕拲堄揰丅
丂 丂丂丂丂丂
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂晽師榊丂丂丂丂丂丂
儊儖儅僈丒晽師榊偺乽搶嫗僕儑僀儔僀僼乿乽搶嫗妝曕乿No俋侾傊丂
儊儖儅僈丒晽師榊偺乽搶嫗僕儑僀儔僀僼乿僩僢僾傊
晽師榊偺乽搶嫗僕儑僀儔僀僼乿儂乕儉儁乕僕偺僩僢僾傊
晽師榊偺乽敧儢妜嶳榌捠怣乿偺僩僢僾傊
晽師榊偺乽悽奅椃乿傊