★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
風次郎のColumn『東京楽歩』
(No365T−85)
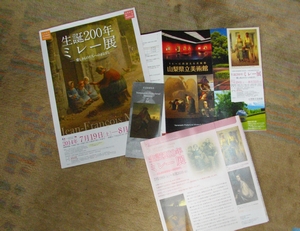
ミレー生誕200年展パンフレッド
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
風次郎のColumn『東京楽歩』
(No365T−85)
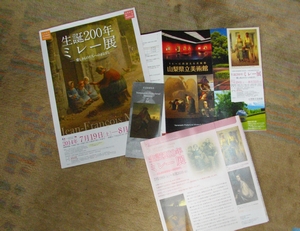
ミレー生誕200年展パンフレッド
2014年8月
東東京楽歩(No85)
ミレー展を観る(山梨県立美術館)
――愛しきものたちへのまなざし――を副題にした生誕200年のミレー展が好評なの
で、富士見に過ごす家族の夏のイベントに皆で鑑賞した。
その日はあいにくの雨模様にもかかわらず午前中から駐車場も一杯になるほどの混雑で、
人気の高さに驚いてしまった。
山梨県立美術館は、開館の頃からミレーの「種を蒔く人」の展示が有名である。私もそ
の頃観た、農夫が広大な畑で力強く種を蒔く姿を描いたあの絵の印象が忘れられない。
今般も、その画家の生きた、素朴な生活の中から画に託した心境の清美を表した作品を
一堂に集めた展覧会は素晴らしかった。
ミレーは8人兄弟の長男として北仏ノルマンディーの寒村農家に育った。生涯忘れ得ぬ
思い出として、故郷を荒らした嵐と、難破した船員のために祈り続けた信仰に篤い祖母の
姿があったという。彼が故郷で培ったのは、「破壊のイメージと人間の矮小さ」に対する
畏れと、雑念から解き放たれ、他人の苦痛を和らげようと尽くす祖母の自然愛だったので
ある。この精神の基盤が彼の絵のエレメントとして生き続けているのだと思う。
『ミレーの絵画に託された田園の理想には、ときには苦役や死の気配が忍び込んでいる。
亡き妻の肖像画が興味深いのは、つねに死や亡霊に怯えながらも、それを乗り越え、自
然の豊穣に向かって新たに踏み出そうとするミレーの最初の歩みが、そのまなざしの脆い
光の中に見据えられているかのようだからである。田園に差し込む近代の薄明りとともに、
生きる手応えと荘厳な祈りの絵画が人々に開かれていく。(石谷治寛26/8/14読売新聞)』
確かに自然の中から生きる手応えを得るには、時を長くして農に励む以外にはないよう
に思う。ましてそれを自分を引き付けて離さない絵画の世界に、顕す憧憬として愉しむこ
とは出来なかったかも知れない。しかし、そこに近づき、そこに勤しまされる力は、祖母
の姿に見る信仰の力であったのかも知れない。
だからこそ、作品の中にさえ、妻と9人の家族に対する父親としてのまなざしを感じ取
ることができるように思うのである。
農業には人間のたちうちできない自然との、それは神秘性をもって成り立つことと向か
い合うところがある。そしてそれは、農業の宗教性に近いよりどころであり、収穫により
倖を得た喜びが素直に感謝へ導かれる所以であろう。
生活の舞台がそこにあったればこそ、ミレーの絵画が現わす写実性は忠実性を越えて神
秘に至る処でもあろうか。
心の和む、時の祈りをそれぞれの作品に感ずるのである。
ルネッサンスを経て、その題材にも自由を得た画家たちは、絵に登場する人物に画家自
身の情感を盛り込んだだけでは物足りず、自然を題材としてそこに目を向けていったので
あった。
ミレーの忠実性は、そののち、時の流れが歩んだバルビゾン派の時代から、浪漫派の光
の表現の時代を経ていく。そしてさらに自由を謳歌した彼らの20世紀の豊かな時代は、
それまで忠実な視覚表現をキャンパスに残していたピカソに対してさえ、様式や形式を超
越して感覚の構成に没頭するといった変化を余儀なくさせたこととも通じていると思う。
もっともピカソの背景には、コートダジュールに遊んだ親友2人(詩人ジャン・コクト
ーと奔放な企業家ココ・シャネル)との交流があり、豊かな20世紀というもっと自由な
時代が始まってはいたが。
19世紀ミレーの絵画はそこに現代画壇の土台的要素を示しているのだとも思う。
あえて、そこに家族への愛が滲み出て含まれることも含めて――。
この展覧会は9月には府中へ移動して開催される由、もう一度行って鑑賞したいと思っ
ている。
風次郎
メルマガ・風次郎の「東京ジョイライフ」「東京楽歩」No86へ
メルマガ・風次郎の「東京ジョイライフ」トップへ
風次郎の「東京ジョイライフ」ホームページのトップへ
風次郎の「八ヶ岳山麓通信」のトップへ
風次郎の「世界旅」へ