
ローレライ
2000.10.7〜14

ローレライ
バスはさっき下ってきたライン川を、戻るかたちで上って行く。
ローレライの真下や、いくつかの城下町を通り過ぎて行った。秋の日差しが川面に反射してキラリと光る。目立った
広告も無く、それが当たり前なのか、観光への配慮が行き届いているのか、河畔の街道に良く手入れされた草木が
溢れ気持が良い。
マンハイムから枝分かれしたネッカー川をしばらく上ると、バスは一旦河畔の街道を離れてハイデルベルクの街に
はいる。中央駅から街の目抜き通りを一当り眺めて河畔に出て止まる。
「カール・テオドール橋」古い橋というのだそうだ。赤砂岩で造られた美しい橋。現地から合流したガイドの説明を暫
く聞いた後、風次郎ははなと橋を歩いて中央の一番高くなったあたりまで進んだ。バスから降りたばかりのほてった
顔に、川風が気持好い。振返ると街並みのすぐ向こうにハイデルベルク城が見える。
山の中腹に、崩れた城壁を見せて立つ。
陽の光はもう斜めで、それが陰陽くっきりと崩れた様をあらわにしている。城の周辺の所々はもう暗い影になったと
ころもある。 まだ夕陽を浴びている街とは対照的に夕暮れの城は幽玄を漂わせ、古城の見映えとしてはなかなかだ。
「随分壁は崩れているんだ」
「しかし、貫禄あるねー」
欄干にすがり二人で古城を眺めるなど旅のもたらす楽しい一時である。
O夫妻もやってきた。
丁度橋の中央は三角形の頂点のような形で袂から盛り上がっており、両欄干には川面に突き出したエプロンがある。
そこが丁度観光客の撮影スポットになっていて賑わう。
「なかなか好いですよ!」
「城ですか?橋ですか?」
「いいや、おふたりですよ。」と軽口も飛ぶ。
橋は比較的広い歩道が設けられてある。それでも普通の車は交差通行ができるのだから、古き昔に造られたとは言
うものの、構造だけでなく優れた構想も伴っていたと連想する。
かった。
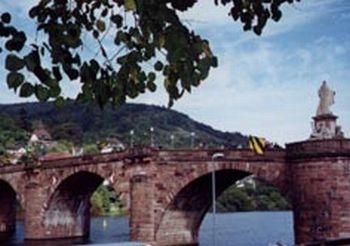
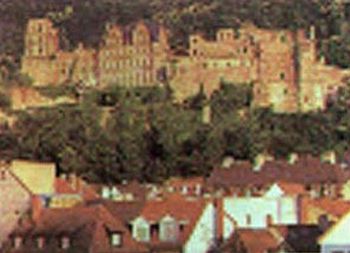
カール・テオドール橋と橋から見上げるハイデルベルグ城
ネッカー川の対岸には緑の中に哲学の道と言われる散策路があり、その昔より人々は川の流れを見つめては歩き続けて多くを語り繋いだのであろう。
この街には大きな印刷機の製造会社もある。世界に先駆けた、産業革命の由来も存在するのである。
街の中へ入っていく。
街角を抜ける先には次の通りの建物が窓を見せて立つ。
ハイデルベルクはドイツ最古の大学、そして学生の街、ゲーテも愛した美しい風景と文化の街である。川筋と山沿に大通りがある外は、人が行き交うに相応しい広さである。
もし石畳に雪の降る街を想像するなら、胸を締め付ける 恋物語もうなずける世界である。
ネッカー川と西岸のケーニッヒシュトール山(中腹にハイデルベルク城がある)の間に町の幅はわずか200メートル、橋から10 0メートルも歩けば正面に最も古いと言われる中世騎士の家に突き当たり、大学の旧校舎と聖霊教会に囲まれたマルクト広場があらわれる。教会は広場の側が礼拝堂の壁になり、反対側の道路脇つまり広場からだと反対の奥の側面に小さな入口があった。普通は礼拝堂の正面に入口の扉を見るのだが、一寸変わっている。広場周辺の道路には、土産物店やレストランが並び、賑わっていた。茲には大戦後の約束で米軍の基地があり、市の人口の三分の一を占めるそうな。日曜日とあって、それらしき家族ずれも多かった。
風次郎は教会に入って見た。
礼拝堂の中は高い天井に、響く小さな音が時折どこからともなく漂うほか、外から閉ざされたように静かである。どこの礼拝堂もそのように正面に向かって、木の椅子が端正に並び、見上げる高窓の明るさは、薄暗い堂内では眩しくさえある。がらんとした空間には世間の圧迫を逃れた安堵を感ずるのであろう。数人の入館者はしばし木の椅子に座り黙している。
入口で伝道師らしい老人が絵葉書を売っていた。中世の写真画があったので購入した。
ハイデルルクの街の家は屋根が赤い。テオドール橋の赤砂岩と同じ色である。それが斜めの陽に光って綺麗だ。その中で大きな教会の屋根ばかりが黒く目立つ。イエズイデン教会の塔を見下ろしながら、マロニエの落葉もはじまった坂道を登って古城に向かう。
橋から見えた崩れた壁のあたりは河畔の街を一望するテラスになっていた。永年の風雪にさらされ、いにしえの戦闘の跡形もそのままに、城壁は哀れな残骸がむきだしのままで、それが古城の凄まじかった歴史を偲ぶ刺激的な風物にもなっているのだろう。眺め見る夕陽に耀く河畔の街となんという好対象だろうか。
遠き国より嫁いできた、王妃エリザベートへの誕生日のプレゼントに、たった一夜で作り上げたため、表部分しか装飾されていないという門が、愛らしく印象的であった。
エリザベート門からつづくテラス側はいわば外城であり、深い堀を隔てて本丸に当たるフリードリッヒ館が建つ。歴代の建築様式が混在し、茲も破壊の傷跡もそのままで大きく壮観である。
地下の奥の部屋には大王が嗜好に任せ、時の権威をかけて作らせたといわれるワインの大樽があって面白かった。観光用に周囲に階段をつけぐるりと巡るのである。ワインも飲ませる。そこには終生守り番として権威を張り、自分はたらふく盗み飲んだという愉快な男の立像があり人気を呼んでいた。戦闘に命を賭けつつも、誕生祝に門を作ったり、大樽ワインでうつつを抜かすのも、壮大なロマンと言わねばなるまい。ワインの樽は城を守る兵士一年分の飲分量だそうな。
その日は市の文化団体のパーティーが大樽の隣のホールで開催される由で、白いクロスをかけたテーブルが沢山並んでいた。こんな所で行われるパーティーも乙なものだろう。
夕暮れの頃、堀伝いに正面の門をくぐる。西洋の城では前にウインザー城を見たが、その時も城郭内に設けられた深い堀に興味を持った。城は戦いの際最後の砦である。場内の深い堀で中枢と外城を区切る目的は何か。例えば最後に攻められ、敵と対決するのに適当な距離を置いた堀に立つて決戦をするのだろうか。あるいは建物と連絡した間道などの秘密路や仕掛けを施すのに特別の役割を果すのだろうか。もっと外の単純な理由でもあるのか。一度調べて見たい。


マルクト広場の市役所 ハイデルブルク城内
『風次郎の世界旅』 トップページへ
南イツ「城巡り」と「ユングラウヨッホ」 4へ
風次郎の『八ヶ岳山麓通信』へ
風次郎の『TOKYO JOY LIFE』へ