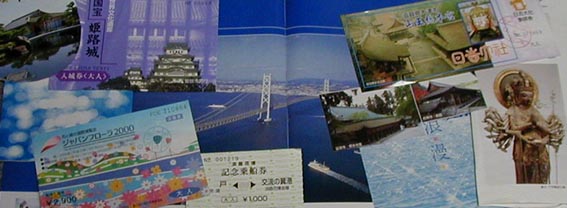
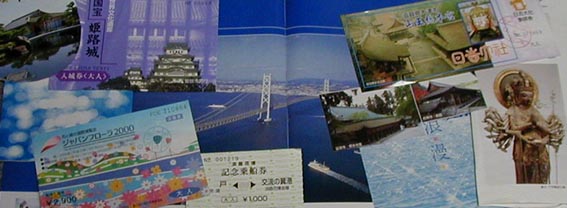
別に特別の取り合わせではない。高槻に住む先輩M氏のお誘いに乗って、花博を見に行って来た。
我が夫婦旅行の3日間行程である。
花の美しいこの春の気分の延長が、花博行きに結びついた。
“ええ、それはいいですね。 ならいっその事、明石海峡の新しい橋を渡り、船で神戸に帰るコースを付き合ってくれませんか。”と、先制攻撃のようなスケジュール手配のお願いで、お言葉に甘えるどころか、几帳面な氏はてんてこ舞いだったらしい。なにせ、人気の花博、しかも私の指定した6月4日は日曜とあって、橋は大渋滞予想、高槻からのバスは満員締切。誠に罪な後輩である。
(6.3)
そんな苦難の押し付けを気にもせず(それでもこちらは多少悪びれた)東京発6時31分の「ひかり」は風次郎と妻ハナを乗せて、今にも降りそうな東海道の海岸沿いを突っ走っていた。
朝が早かったから妻ハナはサンドイッチの朝食を済ますと眠りに入ろうとしている。しかし、出張馴れした風次郎と違って、たまに乗る新幹線の窓景色を見ておかないと損、とでも思っているかのように、時々眼を開けて、窓に額を寄せて眺めている。
風次郎は、車内販売のコーヒーがそう美味い訳は無いのに、どうして何時も美味いのだろうなどと、愚問を繰り返しつつ、紙コップにたっぷりと注いでもらう。
列車が揺れているのは、液体を飲む体に良いらしい?
その一杯をウイスキーを舐めるような飲み方で啜りつつ、日本経済新聞を読み漁る。この姿はまるで出張と変わらない。これでは着ている物が少々違うだけで、仕事と変わらぬ様ではないか。
朝が早かったのは、京都駅烏丸口10:00発の「比叡山と坂本の街散策」=京都市営バスを予約していたからである。
1. 比叡山
ガイドが手馴れた案内で、河原町通りから京阪三条駅の客を乗せると、バスは一席の余裕も無い満席となった。
比叡山へは北白川から白川沿いに登り、比叡山ドライブウェイを行く。大型バスは狭すぎると言いたい程の道を、対向車と窮屈なすれ違いを繰り返しつつ、登って行った。
最早新緑は満ちて、谷に寄り落ちかかる若葉が鬱蒼と車窓に迫る。雨こそまだ降らないが叡山へ向かう観光としては、この程良き暗さは幽玄。むしろ雨来れば、荘厳な舞台を演出するだろう。
ところどころに穏やかな白で、光るように山ぼうしが新緑をひきたたせている。
やがて杉と桧の垂直な大木を見渡す山中に入っていく。
バスを降りて国宝殿に入る。
入口の右手に大きな釈迦如来坐像(木造)が置かれ、修行僧の説明を聞く。
成る程、信長の焼き討ちにより多くの貴重な文化遺産は今形を留めないのであろう。が故に、分散した遺留遺産を集合させた意義は大きいのかもしれない。
国宝殿の名称由来は、いわゆる国宝を誇示するに在らず、伝教大師最澄の「山家学生式」より「一隅を照らす、これ則ち国宝なり」より来る、と言うを心得た。
叡山は大比叡山(848m)四明山(839m)の2峰から成る。天台宗総本山延暦寺は延暦四年(785年)に最澄により起こされ、元々比叡山寺であったものを弘人14年(823年)嵯峨天皇の勅により延暦寺と改称されたのである。
信長の権力をもってして制する程の僧兵の力の存在、其の制圧の後、再び秀吉が復興を命じた等歴史上も重要な聖地である。
風次郎は数年前、高野山に一時滞在した折の宗教的感慨が、往時双璧と言われた該宗派の修験道場では如何と、かねがねこの延暦寺を訪ねる事を期待していたのである。
杉、桧の高木密生し、峻険な尾根と谷が激しく重なった山塊は、京と琵琶湖という比較的恵まれた里を近くしながら、たしかに修験者たちへの厳しい環境であったろうと思う.
一方で、新しさを隠せない国宝殿や道路の配置、そしてその人口壁などの目に触れる様が、信仰に対する現代の軽さを見せているようで少し気落した。
もっとも、修験というのはもう一段奥を読めば、当時としても花の都に近く、農漁豊かな琵琶湖を控えて、俗物、俗界に身をさらしつつ、高徳を求めるという類の事であろうから、風次郎のように、周囲の雰囲気に囚われやすいのは、それこそ俗者といわれるかもしれない。
ガイドの話を聞きながら、やわ土の段をはさんで続く階段を下って、根本中道に入る。
彼岸をあらわしたという拝殿の向こうの、一段と低い処で行われている修行。火花を飛び散らせて修行僧の護摩を炊く姿、そこから漏れ来る読経の朗々たる響きは、風次郎を納得させるに余りあり、拝殿に立ち、拝観者に語る僧の姿も仏の教えと共に好もしかった。“人彼岸を渡る”との説教を聴く。
すなわち叡山は「思いやりの心をもって、一隅を照らす人をつくる」修業場であり、鎌倉仏教の祖師多くを出したのであった。

雨が降り始めた。
一行はケーブルカーに乗って山を下りる。かなり急な、杉の立ち並ぶ斜面を、早い(そう感じた)スピードで一気に降りるという感じだ。雨に沿線の若葉がぬれて、車窓を光り去るさまが印象に残り、叡山を懐かしくするだろう。西塔、横川などを割愛して山を降りるのは惜しい。
2. 坂本
坂本の「芙蓉園」に昼食が用意され、池を中心にした名園に面した和室に案内される。
庭は、其の池に滝をあしらい、近江の奥座敷から眺めると言うに相応しい風情である。
卓上は京料理、ゆばを中心に六角重膳。美味である。
この坂本の街は延暦寺や日吉大社の門前町。両寺社に因んだ寺社は元より、高僧が過ごした里坊(山の上の山坊に対する呼称)が多い。仏教の教えは「心を落ち着けて景色を見る事で悟りの境地に達する」という。その美しい景色を庭園に求め、里坊や神社、又古い民家には石塀が多く造られたという。この地に伝わる天然の石を、巧みに組み合わせて築く穴太衆(あのうしゅう)積みが、この街の趣を高める。芙蓉園も元里坊であった。園全体が洞穴を伴う代表的な穴太衆積みで囲まれ、坂本の名勝として残っているのである。
丁度昼食の間に雨が上がった。
坂本の街散策も観光コースのテーマであり、2時間あまりが自由時間として与えられているので、私達は日吉大社と西教寺を歩く事にした。
風次郎の住む近くにも、日吉神社があるが、その本宮がこの坂本に在るとは知らなかった。ご縁は疎かに出来ないと呟きつつ、ハナと二人でぐるり参拝した。東西本宮のほかに、幾多の末社があり、神輿の倉があったりするが、建物は修理が追いつかぬ体が多く、屋根なども応急にカラートタンを挟んであったりして、痛々しい感がある。神様にも体を繕うにはお金が必要なのだ。
そもそも叡山は、山頂にオオヤマクイノカミとオオナムチノカミを祭るそうな。延暦寺が出来てから、その佛徒により有名を馳せ今日に至るが、本来日吉大社のご神体であるという。東本宮オオヤマクイノカミは五穀豊穣の、西本宮オオナムチノカミは国家鎮守の神として、日吉山王権現(近江一ノ宮)を称し信仰を集めていた。天智天皇七年(668年)大津京奠都を偲ぶことになる。
延暦寺勢力の強大化は神仏習合が進み、本地垂迹説(ホンチスイジャクセツ=神は仏の仮の姿)により、僧兵等からも担がれたという神輿(再建の物)も庫に安置されている。今も伝わる祭りは勇壮であるそうな。しかしここも信長による焼失は免れなかった。
手にした古地図の境内は広大である。西本宮への参道を上がり、東本宮へ渡って、東本宮の参道を下った。幸いにして陽が差し込んで来た。
天台から1878年独立したと言う天台真盛宗総本山「西教寺」へ足を向ける。
境内も其れなりの風格在り山門から参道に沿って続く数ある坊の夫々に、独特の迎え屏風(又は置き飾り)が施され、興を引く。
聖徳太子の開創であり、やはり信長に焼かれている。その後坂本城主明知光秀が再興に力を尽くし、修業に通った旨記されていた。光秀は此処に心を寄せて親しみ、対信長で悩んだ在所であろう。
長い参道の往復は夏の午後の陽が、真っ直ぐ立つ杉の幹の間から斜めに差し込み、巾長の石段に落ちる。年表に光を当てて辿るがごとく石段を降りる。滲み出る汗を覚えつつ古きを偲ぶ。。
西教寺からバスの待つ芙蓉園までの2キロ程は、一般道より西より山の手斜面に残る旧道を歩いた。左に琵琶湖を眺めるこの斜面に点在する家々は、構えも厳かで、古来の豊かさを物語っているようだ。きちんとした(新しくない)石垣、門構え、そして庭の手入れである。その昔は山を越え京都の街の庭造りへと向かった庭師の家のようでもある。つつじや、あやめの花が咲いている。
坂本から京都へは左手に琵琶湖を望みつつ、山科から東山を越える。
バスの揺れも好い物だ。うとうとと、今過ごしてきた坂本の風景を思いつつ、旅の気分にさらに浸っていく。
山から見下ろす京都は又少し霞んでいた。
3.ジャパンフローラ『淡路花博』 (6.4)
M氏宅の向かいの犬が吼えているので目が覚めた。
かなり離れた通りを行く救急車のサイレンが気になったようだ。
風次郎の家の犬もあのサイレンには弱いと言うか、合わせて鳴く。ハナの話によると、ピーポーピーポーは、犬の叫びを誘発する音波であるらしい。
五時前である。家の外を見ると好天である。
昨夜飲み過ぎたのか、我等がスケジユールの諸手続の気疲れか、M氏は持病気味の腰痛が激しく、今日は留守番にまわると言う。花博へはM氏夫人と私達の3人で行く事になった。
申し訳無さと、仕方なさを言葉に表し、一宿強飲の礼を述べて、朝日の当たる丘の上の住宅地を下りる。
日曜日の朝、高槻の街はまだ静かな七時前である。タクシーの道路選びも自由自在のようで、駅まではほんの5〜6分で着いた。
風次郎はM氏欠席の列車の切符の一人分ももったいない思いで、列車の出発時間を確かめると、出札所へ走る。¥800の払い戻しがあった。M氏夫人にこれを渡すと彼にとって、少々安堵の自己満足を得る。気分が好い。堅実は宝だ。
三の宮からは、M氏奮闘の結果得られた淡路洲本行きのDXバスに指定席が確保されており、3人はゆったりと身を沈めた。待望の世界一長い吊橋「明石海峡大橋」を渡って行くのである。
市内から舞子に至る高速道路は、海岸沿いに走っている。高架の上から見る街並みは、かつての地震の名残が、化粧直しをしたビルの表壁や、建て直されて真新しいビルの多さによって、むしろ偲ばれるのであるが、知る者が知る感傷以外は何も無い。近代的ビル群が続いている。
朝の港風景は少し霞みがかって、日曜日の穏やかさを漂わせているようだ。
地震の時、ズタズタになった高架道路を思い浮かべるとゾッとするが、そんな事はまるで嘘だったようにバスは快適に進む。やがて明石海峡大橋にかかる。
橋そのものの形に特にユニークさは見られない。横浜のベイブリッジや東京湾のレインボウブリッジなど、最近の吊橋は、殆どが自定式(ゴールデンブリッジ型)である。大きな橋といえば大体がこの型になって見慣れてしまった。
この橋を渡るとそれこそ淡路へ直結すると言うというところに意味がある。数年前、明石から淡路へやはりハナとの夫婦の旅で四国を巡る旅に渡った時は、フェリーであった。その時も淡路から徳島にかかる鳴門海峡大橋に胸をワクワクさせたのであるが、今度は世界一だ。
吊橋はバランスによって形が成っているところが美しい。又橋であればこそ渡ったという経験に大きな意義があると思う。
橋の向こうには夢があり、こちらの世界と異なる何かが期待できると思うからだろう。
仏教だって、「彼岸に渡る」と、つい昨日延暦寺での説教を聞いたばかりだ。
世界一の吊橋、全長3911mの明石海峡大橋はバスで渡ると通過時間ほんの4〜5分だった。
空は少々雲を増し青空の下のくっきりした風景ではないが、海は穏やかに色薄く、橋を吊る格子模様のロープの向こうに広がる。
そしてジャパンフローラ「淡路花博」の会場が、車窓左手にぐんぐんと近ずいてくる。
花を見に行く旅。
何と柔らかな、品の良い旅だろう。第一聞こえが良い。ゆったりした身分の者の旅のように聞こえる。
思い過ぎか?いや良い、自己満足でも。
あえて花を見にわざわざと、と言うならば、観桜、あやめ苑、皐月苑、牡丹苑、観梅、そして幾つかの植物園などは、散策のコースとして随分歩いている。が、旅として、又博覧会を一日かけてというのは、風次郎には初めてである。
一体どんなに多くの、どんなに珍しい花が、その美しさを伝えてくれるのかと、期待の内にバスは会場に直結の停留所に止まる。
その場が博覧会場である。下車と同時に眼前に広がる海を眺めながら、斜めの坂道を下った。その坂道をプロムナードガーデンと呼ぶ。
今日の道中は、M氏夫人と妻ハナ、女性二人、両手に花の花博だ。そう艶やかとは言うまい、そこを語るのはよさねばならない。
今頃M氏は、自宅で腰をなでなで新聞でも読んでいるのか、それとも昨夜からワイワイした風次郎型タツマキが去った安堵で、高鼾だろうか。
それにしても、降り立った一瞬、軽い潮風に身を晒して、ワイドな花景色を味わう機会が一緒でなかったのは残念である。軽妙な関西弁の解説が欲しいところであった。
M氏夫人は2回目である。広い会場の様子が解っている。これほど有り難いことはない。
一日で見るべきは何、を決めるのも難しいばかりか、広い会場を歩くのは疲れが伴うから、くまなくと言う訳にはいかない。私達は彼女の案内をたよりに、「百段苑」、「奇跡の星の植物館」を周り、トラムで会場を巡り、最後に各国の花庭園を眺める日程を撰んだ。
M氏が言っていた。
“雨でも降ったらエライコッチャ。ヨケイ人が集まるし、ホナモン、何処にも雨よけがアラヘンノヤ”
“昼飯クウンニモ傘さして、立って食ワンナランデナ”
人はどんどん入ってくる。私達がバスを降りて園内に入った頃は、まだ疎らだったのに30分もすると、未だゲート(有料施設)が開く前にもかかわらず、もう100mの行列である。脇のゲートにしてこれでは、正面や南のメインゲートはさぞ早々からの混雑であったと思う。まして日曜日だ。
少し陽が射してきた。傘さして昼飯の立ち食いはしなくて良さそうだし、又カンカン照りだと日傘を使う程だろうが、丁度良い照り加減で、その必要も無さそうだ。ホットした、本当に。

M氏夫人の解説通り、「百段苑」と「奇跡の星の植物館」は必見の会場のようだ。
百段苑は安藤忠雄の設計だという。有名な人の設計だと有り難いような気がする。高低差100mの土手(工事前は崖であったろう)を上手く使って、枡形の花壇を無数に貼り付けたように配置し、五大陸の菊系の花を植えた。その間を巡回して眺めるのである。かくも色々な菊の花があるのかと驚くばかりか、菊は世界中にその種が広がっており、寒さにも、暑さにも順応してさいていることが、現実の事として解る。それ故、初夏のこんな時に菊が楽しめる事を喜ぶ。
難しいカタカナ国名、地名と並び、説明札に書かれているが、なかなか覚えられない。かろうじてアジアのノアザミ、ウスユキソウ、アサギリソウ、ゴボウ等の名前に親しみを得られたのである。
この花壇、プロムナードから入って、上から眺める光景がよい。枡形毎に、それぞれの花色がコントラストを見せる。まるで色付き千代紙を置いたように、色彩のパレードである。但し、この斜面を降りて、下から見上げるのは、斜めの花壇とはいえ、花を植える傾斜に限度があるため、花の美しさを伝えて来るものは無い。花壇の壁と通路のモザイクを見るだけに止まると思ってしまう。
奇跡の星とは地球である。名前だけで、メルヘンの夢物語を想像し、さぞかし変わった美しい花や、驚異の世界を期待する。従ってこの「奇跡の星の植物館」の人気は一日中入場者に待ち行列を作らせる。それを見越して、開館と同時に入るべく並んだが、やはり入場制限一回まち(5分位)だった。
3階建ての巨大なビルの中に、植物の形、色、作用、特性、それぞれに注目すべき処を集めて見せている。
暗い空間に活発な成長を続けるシダ植物群の不思議。へんてこな形で植物とは思えないような奇妙な花木。
やはり暖かな海に近い国の物たちのように思えた。
それらは最早多くの人の集まる施設だけでなく、ガーデニングに取り入れられ、家庭でも愉しむことが出来る程身近にあるようだ。動物とのコミニケーションのように、本当に植物との対話のようなコミニケーションがありそうだ。
トラムに乗る。これが一番効率よい。
会場は何といっても12ヘクタールだ。一日歩いているのは健脚の若者でもこたえるだろう。
トラムもほぼ何時も行列だが、それでも10分位列べば、これに座ることによて、園内主要部を一渡り眺めることが出来る。池のほとり、各国式庭園、小高い丘、それは手入れされた芝生の緑と、それなりの木々が植えられ、道路に沿って無数の花が咲き連なる。
多くの参観客が道を、草原を埋め、仲間で、家族でと老若男女喜々として寛いでいる。トラムでその中を行くのも悪くはない。
メインゲートまでトラムを使い、テーマ館のテントで世界のミニ庭園を楽しみ、屋外の国際庭園を一通り眺めた。庭園はやはり歩くのがよい。
風次郎の感想では、何処の国のも置物が少し違う程度で、あまりユニークな印象はなかった。目を見張るような物を期待するのが無理なのかも知れない。-----雑踏で疲れも出てくる。
遅くなった昼食を採る。
全く人が多い。芝生の場所確保も、事によったら苦労することになりそうだ。M氏の“傘さして立って飯食ワンナラン”になってしまう。それに弁当購入や、出店しているカフェテリアもごった返しており、“おにぎり弁当”は的中である。美味かった。と同時に「関西弁アドバイス」に感謝感激で口調を思い出しては苦笑いを隠せなかった。
「如何ですか? 腰の具合は、」
「ああ、どうにもならん。まあ、家の中やから、ボチボチやっとんねん。」
「こちらお陰さまで、天気も申し分なく、カンカン照りでもないし、雨もふらんし、楽しくやってます。」
文明の利器、携帯電話でM氏と話す。氏も、夫人を案内役に取られ、急拠の在宅では、腰も痛いし昼食にもならないのでは?と思った。悪いことに、氏は梅干しが苦手だという。夫人は3個づつ、3種類のおにぎりを作って、急拠欠席になった氏の昼用に2個置いてきたから大丈夫と言ったが、おにぎりには印が付いていない。3人で7個全部を食べたが、その中には梅は一つしか入っていなかった。結局、残りの2個がM氏に宛われたことになる。“一体M氏はどうしただろうか?”
腰は痛いわ、昼になったら嫌いな梅干しだわ! ヤケクソになっていたのではあるまいか。
風次郎は気が引けて、その事は未だに、聞き正してはいない。
兎も角、私達の昼食はおにぎりが正解であり、野外弁当は実に美味かった。
どっぷりと雰囲気も味わい、見る物も満たされ、ゆっくり野原の昼寝を愉しむ。
南ゲートの外、ウェスチンホテルのグリルで午後のコーヒーを楽しみ、ラッシュ前の船に乗る。
デッキに設けられた座席から眺める淡路の島は、この花博会場のみが沸き立っているようだ。緑の島に近代建築の白が光り、人の気を引くデコレーションの色模様が華やいで連なる。スピーカーの音楽も聞こえてくる。
この山の土が、関西空港をつくり、生活を便利にした。そして今度はイベントにより、神戸の経済復興のエンジンを掛けるという構想である。チラと昔の週間紙記事が脳をよぎった。
どちらにも何も文句は無い。文句なんかあるもんか。人それぞれの思惑で生きているんだ。
そう言うと、却って文句があるような言い方にも取られるが、世の中何が良いかなど、その時々の勝手に因るものだ。
些か海を見ながら、思いの勝手が大らかになった。
何を言おうと、地震によって被った生活の悲劇は、其れを知らぬ者に語れる余地はない。
神戸復興は、国全体の仕事であった。そして今、それはその順序として、地元の問題へと移ってきたのである。
船は速いスピードで、真っ直ぐに神戸港中突堤へ向かっていく。左彼方に、朝渡ってきた明石海峡大橋が少し霞んで見えている。
“ああ、良かった。橋も、花も、船も、それに天気も。”
時々高い波を切って進む船の脇から、しぶきが飛んでくる。若者は歓声をあげて其れを避け、子供は喜んで水を被り、ある者は席を退き、又ある者はそのまま在るに任せる。
風次郎も、在るに任せる年になった。そう在りたいと思った。そして隣を見る。M氏夫人もハナも同じ様態であった。
船が港内に入り、中突堤に接岸する頃、不思議に又陽が射してきた。
不思議というのは、今回の旅は必用な時に降り、必要なと時に曇り、ほしい時に陽が射すのである。
これは決して小説ではない、事実なのだ。
爽やかな夕陽を浴びて、M氏夫人と手を振って別れた。
5. 姫路城 (6.5)

十時に姫路駅でK氏に会うことになっていた。
K氏は、風次郎の会社の同僚であったが昨年、岡山の有力教育産業オーナーに請われて、その経営に参画している。現役時代から、久し振りの再会である。
姫路城は、ハナがまだ見てなかったので、この機会に足を延ばして訪れたいと連絡を取ると、今日の案内役を買って、わざわざ岡山から来てくれると言う。感謝感謝!
神戸の中突堤のホテルの朝は、南向きのバルコニーから射し込む朝陽に起こされるような、爽やかな目覚めであった。
好天。月曜日の朝の事だから、港出入りの船が賑わうかと思ったが、私達の絶つ8時前までは至って静かで、穏やかであった。シャトルバスが神戸駅まで送ってくれた。
東海道線の終始点となる歴史ある神戸駅は、規模こそ近代のターミナル駅に及ばない。しかし、時代を担ってきた貫禄は、窓に壁に、雰囲気を伝えている。
駅舎のコンコース両側にレストランやカフェがあり、その中から朝食を採る為に、外の景色も楽しめる角の店を選んで座る。
改札に向かう通勤ラッシュの人々も、それほどハードに見えない、東京には無い余裕を感ずる。
今回、風次郎は山陽電鉄を利用して見たいと思っていたので、高速神戸駅へ向かう中、伝統を伝える神戸駅の姿を眼にしたいと立ち寄ったのである。
山陽電鉄の特急を待つ。高速神戸駅のホームは地下である。駅名は成る程、地下鉄を神戸高速鉄道と呼ぶのであった。しかし、ホームで待つ15分間には、地元私鉄数社の列車が順繰りに発着する。線路は各社相互乗り入れが行き届いているらしい。よい事だ。こんなに数社が走る路線は少なくも東京には無い。合理的である。
8時50分発の山陽姫路行特急に乗る。
神戸に着く列車は、何社の何線から入ってくるにしろ、それなりに満席で来るが、ここから西へ出発する列車は皆空いている。特急もしかりである。駅員も言っていた。JRの方が姫路までだと20分は早いそうだ。ただ、これは姫路へ行く場合の理由にしかならない。
ゆったりと背もたれに寄りかかり、しばし車窓を楽しむ。しかし、何も変わった発見も無く、すぐに車両の揺れに身を任せてうとうともする。これと言って変わらぬ日本の風景の中に、あまり地域の季節感や風土の趣を求めすぎると、大したものは無い。
もっとも、東京から来て(出張などで)、この地を在来線で通る事も少ない。殆どが新幹線でトンネルだし、時間を考えれば飛行機である。
そんな訳で、今回は貴重な在来線、しかも初体験の私鉄に乗ることに意義を認めているのである。
正面に城を仰ぐ姫路駅に降り立つ。
同僚は有難い。“よう!”と肩を叩くだけで一切の挨拶を終える。万感の思いは序々に表していけば良い。
すぐにタクシーに乗って城に向かう。K氏も元気だ。城には、来訪客を案内して度々来るのだと言う。
彼は、人柄も良いし、仕事の切れも見事で、持ち前の能力も、あらゆる分野で光っていた。今、出身地岡山で地元活動の仲間との交流も深め、父母を労わりつつ、有意義な人生の仕上げをしているように見える。
風次郎の地元、八ヶ岳に一度登りたいと、東京を離れてから計画した事があったが中断した。その頃は忙しく、まだ今も実現していない。この元気さだと、まだチャレンジできるかもしれない。
姫路城は何と言っても本丸、天守閣の幾重にも重なる瓦屋根と、白壁の端正である。それに千姫ゆかりの西の丸を、時間をかけて渡る登城が楽しみである。
名城として誇るべき世界遺産である事も勿論だ。
大手門から見上げる今日の天守閣は、青空の下、初夏の陽光に輝き、見慣れても尚飽かせない美しい威容を見せている。三の丸広場の芝生の緑から堀を隔てて、石垣上に聳える城郭は、白鷺城の名の由来を頷かせる、白の主張が眩い。
新緑は共に輝きを放って、正に季節の妙を奏でる。
やはり西の丸へ靴を脱ぎ、磨かれた渡櫓の回廊を歩く。
隅櫓の数々、長局、そして千姫の化粧櫓。小窓からは、遥か海まで続く街並みや、裏手内陸に続く山々を望み、往時を偲ぶ。
さすがK氏は史実に詳しく、親しく解りやすい説明がつく。
又、K氏独特の口調で呟く。
「昔も今も、上に仕えるッチュウ心は変わらんジャロのう」と。
この様な城の時代は、人心は一途であったとして良いだろう。つまり思考の枠は、ここに生きる者にとって、野望をもって城外へ飛躍する輩以外の者には余裕も無かった筈だ。
“そこが違う”と風次郎は言うか言うまいか迷っていた。今とは自由の質が違う。
足音以外何も訪れない。その時代の空気が延々と受け継がれているかのように、厳しさを感じさせる距離が、今日の廊下にも存在する。
人が歩くのは「道」であるが、その「距離」は時に生死の差ほど大きな問題となる。人が生きるのは、「時間」なのであるが、人はときにそれをも見失う。
「城の時代」その世の大多数側の人々の感じ方はどんなだったろう。城をもってして、天下を論じた人々の世界とは別物であったのではないだろうか。
いや、この分別は今も変わらぬ相似形であろうと思う。
つまり、支配被支配の枠組みは永遠に続くであろう。差別も、弱肉強食も、果て又、共産も民主も、専制も相互扶助も、生物在る限り続くものであると定義することになる。
延暦寺の説教を思い起こし、仏教の彼岸の思想をここに理解するのは如何とも思う。

天守閣に登る。
民衆を象徴へ導く威容である城郭、かつ又、この樓を最終戦略基地として戦ったその時代を、何処の城へ登っても思わずにはいられない。
城を持つ時代は、機能の違いこそあれ、和漢洋何れの地に在っても、対戦上の考え方、築城思想は変わらなかったと思うのである。
今の風次郎は、天主では、その地形を眺め楽しむに過ぎない。
息を切らして登り、最上階で味わう平時の風は、古今を問わず清々しいものである。あったろう事に変わりはない。
この城で何時も気になるのは、天守閣の脇に「腹切丸」が在ることである。何処の城にもこういった場所が在るのかどうか、調べたことはない。腹を切るのは通常は咎を責められる人であるが、このような要所に場所が置かれたことはどう理解すべきだろうか。そのうち調べてみたい。
K氏は写真も上手い。手持ちのカメラで私達のスナップを何枚も撮ってくれた。また、自分がその昔、この城の白壁と屋根のカーブを撮り、入選作を得たことを語ったりした。
現代の城は、多くの人が訪れ、それぞれに思いを残す所となったのである。
城外に新しく出来た庭園の館で、名物の「あなご重」を昼食とし、茶室の本格的お手前による一服の茶を戴きながら、K氏との昔語りも暫しのこと、午後1時50分発の列車を予定していたので、切り上げた。
くよくよはするが、常に明かるいK氏である。話が健康的で嘘のない善人であることに敬意を表し、決して策に溺れることのないところを生かして、自分の世界を守って行ってほしいと、風次郎は親愛のエールを送りたい。
城は美しい。その城を見る度、人の一生は戦争で明け暮れずにありたい、生涯が、戦いであってはならないと思う。むしろ、どう愉しむかに明け暮れていたい、と思うのが、何時もの心境である。
乗り込んだ新幹線はアッという間に東京に帰ってしまった。
ホームページのTOPへ
望岳へ
山麓漫歩へ
Galleryへ
風次郎の武蔵野へ